

歴史
大山寺を中心に栄華を誇った繁栄の歴史に注目
大山の名前が初めて文献に記されるのは、奈良時代に編さんされた「出雲国風土記」。
その当時は「大神岳」や「火神岳」と記され、古来、「大いなる神の在ます山」として、人々に崇敬されてきました。
古代の歴史といえばお隣り島根県の出雲。
実はココ大山は、国引き神話とも密接な関係があり、八束水臣津野命(やつかみずおみづぬのみこと)が国引きのため、引っ張った綱が今の弓ヶ浜半島や出雲の長浜で、その綱をつなぎとめた杭が、三瓶山(さんべさん)とココ大山だと伝えられています。
時を経て、大山が栄華を誇った時代があります。
それが3000人の僧兵を抱えたとされる鎌倉時代から室町時代にかけての「大山寺」。
このころは高野山金剛峯寺(和歌山県)や比叡山延暦寺(滋賀県)と並ぶ大寺となり、その勢力は強大に。信仰の舞台として崇拝され、この地域の中心として大いに栄えていました。








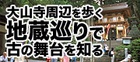
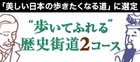

2018年(平成30年)に開山1300年を迎えた大山。
古くは、修験の霊場として、三徳山(三朝町)とともに絶大な勢力を誇った山岳寺院は、最盛期、三千人の僧兵を抱えるなど一大勢力を誇りました。